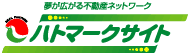『不動産業』っていつから始まったの??

こんにちは!未来LIFE HOMEです♪
今回、不動産売却専門サイトがオープンいたしました!
それに伴い、こちらのブログでは、不動産に関する情報など、定期的に載せていこうと思います(^^♪
さてさて、不動産売却、、、不動産を売るということですが、いったいいつから始まったのでしょうか?(・・?
なんとなく気になったので、調べてみました!
『不動産業』が始まったのは、江戸時代から明治時代。
江戸時代には大家業が行われており、明治時代には土地などの売買が始まったそうです。
ですが、それ以前にも土地に関する制度はあったようです。
飛鳥時代
最初にできた制度は飛鳥時代の645年。社会の授業で耳にしたことのある「大化の改新」を機に、【公地公民制】という制度が始まりました。
公地公民制とは、土地と人民はすべて国の所有とし,私有を認めない制度のことです。
人々は土地の所有ができないため、国から土地(農地)を貸し与えられ、その土地で収穫したお米の一部を「祖」(税金)として国に治める義務が課せられました。
また、貸与された土地は一代限りで、当人が亡くなるとその土地は国に返却されるため、相続や売買はできませんでした。
これは【班田収授法】という仕組みになります。
奈良時代
723年、【三世一身法】が発せられました。三世一身法とは、新たに用水路を作って開墾した者には本人・子・孫の3代まで土地を貸し与えるというもの。
班田収授法が条件付きで、長く利用できるようになったというイメージですね。ただし、実際にはあまり効果のない法律だったようです。
その後、743年、農民が新規で開拓した土地について、永久に所有を許可するという法令【墾田永年私財法】が出されました。ここで初めて個人が土地の所有をするという形になりました。飛鳥時代の公地公民制はこのときに崩壊したことになります。
土地を所有して祖(税金)を納める=固定資産税の原型のようですね。
この後、武士も登場し、不動産と歴史の密接な関係がどんどんわかってきました。
昨年、話題となった大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも出てきた鎌倉幕府。今年の大河ドラマ「どうする家康」にも出ている豊臣秀吉。
そういった時代のお話も出てきますが、今回はここまで。
また次回、よろしくお願いします♪(^^)/
鹿児島市の不動産売却なら、上荒田町の未来LIFE HOMEへ♪